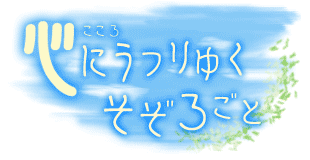 |
|
| /そぞろごとトップ /検索 /管理用 | 松本医院Home |
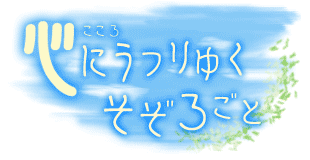 |
|
| 第92段:脳死と移植 |
日本での脳死と臓器移植の話題もとりあえず沈静化していますが、そもそも脳死を認めるかどうかということが移植と関連付けられて論議されていることに問題がこじれているようですね。
脳死を認めるかどうかについては脳死を認めざるを得なかった時代のことに戻ってみる必要があります。
私が学生時代に聞いた話ではイギリスでポリオを発症した患者さんに人工呼吸器の「鉄の肺」と呼ばれる装置をつけていたのですが、この装置を装着すると脳死状態でも呼吸は続いているため、生きているように見え装置がはずせない状態でした。
そのような場面にその装置を使用することで絶対助かりそうな患者が運び込まれ、使用できる装置を全て使用しているときには、運び込まれた患者さんはみすみす死んでしまうという状況が出現しました。
次の救える患者さんのために死んでいる人のために装置を動かしつづけるのは不合理という考えが定着し、そのために間違えのない脳死の基準を作り国民の合意を形成していった過去があるとのことでした。
移植医療とは全く別の観点から脳死を人の死として認めていたわけです。
日常診療の中でも少なくない患者さんから延命だけの治療はしないでくださいと頼まれることがあります。
脳死を認めるという立場での発言ではないのですが、根底には自然な形で死にたいから器械や薬で必要以上に長生きさせてもらわなくてもよいという考えが伝わってきます。
長い入院生活で本人も家族もどこか本来の人間的な生活を失ってしまっているという意識があるのではないでしょうか?
自分たちの家族としての自分が家族としての一員でいれば、治る見込みのないものに集中豪雨のような医療をしなくてもよいのではという疑問があるからではないでしょうか?
昔のインドには布施をする人を「ダーナ」と呼んでいたようです。
「布施」は自分にとってかけがえのないものを差し出させていただく、自らの気持ちで進んで捧げるものなのだそうです。
この「ダーナ」はインドから西に伝わり英語の「ドナー」移植医療の臓器提供者の意味になりました。(大切なものを差し上げる人の意味です。)
東に伝わった「ダーナ」は日本で「旦那(だんな)」になったのだそうです。
移植の臓器提供者は菩薩になり自らの体を布施しておられる、家族も死という別れを布施という形での臓器提供を承諾されているのかもしれません。
脳死や移植医療についてはさまざまなご意見がありますが、輸血はよいが移植は困るとか、献眼はよいが心臓はだめなどというような枝葉末節の論議より地に足をつけた話し合いをしないといけないと思います。