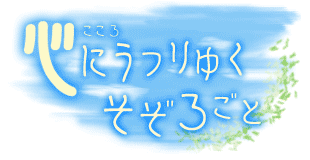 |
|
| /そぞろごとトップ /検索 /管理用 | 松本医院Home |
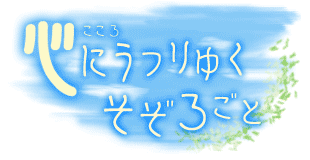 |
|
| 第98段:家庭機能の外注化(その2) |
食事や育児、教育も外注化した日本では、介護保険を導入して老人の介護も外注化することになりました。
社会が介護を保証するというシステムです。家庭の中での老人の介護の困難さは経験しないとわからないものがあります。
単に虚弱になり動けない場合もありますが、痴呆を伴う場合も多く意思の疎通ができないために様々な問題が持ちあがります。
「年を取ると子供になるからね。」と話される方もありますが、子供のように軽くかかえることも不可能ですし、子供は次第に発達し、知恵がつきますが、痴呆を伴う老人は徐々に体が動かなくなり、痴呆が進行します。
教えても、怒っても痴呆の方には何の効果もありません。
介護をする人にはただむなしさが残るだけです。
今から約80年前には親が仕事を引退してから死亡するまで(老親扶養期間)は5.3年でした。約70年たった1991年には20.3年に延びました。
現在高齢者の死亡前の平均の寝たきり期間は8.5ヶ月。
死亡する前に半年以上の寝たきり期間を過ごす人が46%です。
寝たきりということはトイレに行けないわけですから、いわゆる「しもの世話」を最低でもこの期間は毎日、1日数回はする必要に迫られるわけですね。
全国の世帯の人数は1953年には5.0人だったものが、1995年には2.9人になりました。
高齢者と子の同居率も1957年に82%だったものが、1993年には56%にまで下がりました。家庭とか家族というほどの人数が一つの玄関口から出入りしていないのです。
ですから家庭機能も外注化し社会が老人を支えるシステムを作り上げなければならなくなったのです。
1999年の春にあるところで雑談をしていましたら、「嫁が家に帰って老人を見りゃいいの。介護保険なんて必要ない。」と豪語された方がありました。
前述の数字や内容をを話したところ初めて事の重大性に気づかれたようでした。
日本の高齢化は老人が増えるだけでなく、少子高齢化と良くいわれます。
出生率(人口が1000人あたりの年間の出生数)は1947年が34.3人だったものが1995年には9.5人になりました。
つまり最近は人口5万人の市では475人程度しか1年間に子供が生まれてこないということです。
高齢化の進んでいる益田市は1年間の出生数が400人を割る年もあるほどです。高齢者を支える若者も少なくなっています。
極端な例でひんしゅく(顰蹙)を買うことを承知で書けば、不妊治療も家庭内の妊娠機能の外注化と考えても良いかもしれません。
(子供さんを授かった時の笑顔のすばらしさは不妊の悩みを聞いている私は良く知っています。悪意はありません。)
家庭の崩壊などという言葉を聞くとき、どこから始まってきたのか?
どのような事象を指して崩壊というのか?
もう一度考えて欲しかったのです。
当たり前と思いながらしていることが、意外と家庭機能を崩壊させていることにつながっているかもしれないということです。
必要な家庭機能は何かを考え直してみてください。