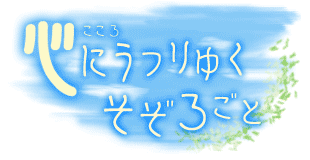 |
|
| /そぞろごとトップ /検索 /管理用 | 松本医院Home |
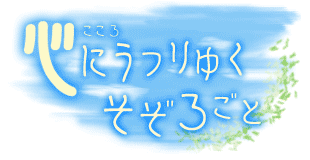 |
|
| 第198段:環境ホルモンの現状 |
環境ホルモンという言葉が一般的になったのはコルボーンらが書いた「奪われし未来」(1997年)のころからです。
内分泌攪乱化学物質(ないぶんぴつ・かくらん・ぶっしつ)とも呼ばれるもので、環境汚染物質の中で内分泌系(ホルモン系)に影響を与え、野生生物の生殖に異常を起こしている例が世界各国で数多く報告されています。
そして野生動物や実験動物に疑いのある環境汚染物質を与えてみると自然界で観察される異常が同じように観察されたことで可能性が強まりました。
人間では実験という手段が取れないことと、人間の寿命が長いこともあって正確な結論が出るまで待つということはできそうにありません。
現在いくつかの化学物質がホルモン系を攪乱させる可能性が考えられています。
この言葉の言い回しがポイントです、「人にとって完全な内分泌攪乱物質です。」とは書いておりません。
「疑いがある」あるいは「非常にその可能性が高い」としか科学的にはいえない状態だということです。
アルキルフェノール類といわれる界面活性剤は環境ホルモンとしてでなく他の面でも人体に影響を与えているようです。
プラスチック可塑剤といわれる物質の中でビスフェノールAも強く疑いがもたれています。
DDTやDDTの代謝物などの残留性の高い農薬なども環境ホルモンの可能性があります。ゴミ焼却炉で一躍有名になったダイオキシン類も環境ホルモンとしての作用が強く疑われています。
(塩素を含んでいるものを燃やすとダイオキシン類が発生しますので、これが混乱を増長させています。ダイオキシン類はタバコの副流煙にも含まれるということも知っていてください。)
疑われているものは他にもたくさんありますがこれ以上は省略します。
これまでは環境汚染物質は毒性が弱く分解性が高い物質なら低濃度に希釈すれば問題ないと考えれていました。
ところが最近になってどうもそうではないという証拠が出てきて研究がされている真っ最中です。ですから昔から危険だとわかっていたものを放置していたのではなく、最近になって危険ではないかと疑いがもたれるようになったのです。
有害な可能性が否定できないとか、有害な可能性があると報道されるとすぐに規制強化、健康診断の実施など様々な要求がなされますが、どのような変化が確実に現れるのか、どのような検査を実施してそれを判定するのか、どこを基準値として決めればよいのかなどがわからないので益々我々を不安に陥れます。
人が一生涯その物質を体に取り込んでもそれが原因で死亡する人が10万人で1人以下にするというのが国際的な規制濃度の目標です。
疑問のもたれている物質のほとんどがまだその基準値さえ検討中というのが現状です。
怪しいものから順に使用を止める努力をしなければならないでしょうが、その順番や対策すらまだできていないのが現状です。
私たちは様々な科学技術に支えられて生きています。その恩恵の浴していることを時に忘れているようですね。
不自然な化学物質や文明の利器で昔の人が考えられなかったような豊かな生活をしていますが、その代償に環境ホルモンのようなものとも取り組まなければならないのです。
環境ホルモンの問題が解決するころにはさらに新しい問題が出てきて頭を悩ませるのでしょう。