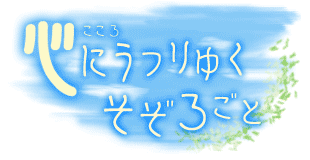 |
|
| /そぞろごとトップ /検索 /管理用 | 松本医院Home |
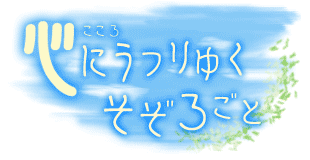 |
|
| 第241段:熊とあう日は? |
8月上旬に札幌市で円山動物科学館館長の長尾章郎さんの話を聞く機会がありました。
その中で北海道のヒグマが飲み残された缶ビールでアルコールの味を覚え、人家に入り冷蔵庫をあけてビールを飲むという話や、森の木がネズミにかじられる被害が多いので原因を探したら、森のねずみの天敵であるキタキツネが人里で残飯や果物を食べに出てきて森の中で食べ物のネズミを探さなくなつたためだろうという結論になったなどと話されました。
餌付けをするつもりではなく、ちょっとかわいいからと自分が食べている食品や果物、ジュース、アルコール類を動物に与えることが、森の生態系を壊していることになっていたと改めて知らされました。
益田に帰って診療を再開してみると、「先生疲れましたよ、この暑い強い日差しの中で猪の柵を作るのは女の私だけですから、こんなにくたびれるのだったら猪に米を食わせて、自分の食べる分は買いたいくらいです。」と話して受診された患者さんがありました。
考えてみると昔は最近のように猪の柵を作ったり網をかけたりということがなかったような気がします。
山中の自然の食べ物は人間の作る作物や貯蔵している食品と比較すれば味では絶対負けるでしょう。
動物がこれらの食品(餌)の味を占めれば手に入るのが簡単な方を選ぶのが当然でしょう。
智恵のある人間だってファーストフードを利用し始めれば後戻りするのは簡単でないように、動物にだけそれを求めるのは無理な相談です。
山の中に餌がなくなったのか?
動物の数が増えて里に出始めたのか?
人間の作った食べ物に惹かれて出て来るのか?
私にはわかりませんが、北海道の話などを参考にすると、様々な変化の発端はどうも人間に原因があるようす。
愛情やお近づきの表現方法の一つに食べ物を与えるというのは動物でも人間も見られます。
また違う種類の動物同士でも食べ物を介在させてお互いが共存するのはペットと人間の関係でも見られる状況です。食べ物のもつ力は大きく、言葉を必要としないので餌を与えてくれる相手は自分の味方や仲間と判断するのではないでしょうか?
美味しい餌がかなり危険な目に遭わないと手に入らないのなら彼らも自重するのでしょうが、日本の人間社会は自分たちの食料を必死で守る生活形態ではありません。
自分たちの生態系や環境のことを考えながら行動できるのは人間の中でも一部の人のようです。
野生の動物を見てかわいいと感じると餌をやりたくなる心理はよく理解できますが、もう一度考え直さなければいけないのでしょう。
診察室での診療が一息つくと訪問診療に出かけます蛇やカエルだけでなく、時には猿や猪にも出会います。
「熊に注意」の看板にも最近は見かけますので。
熊の顔をしたお医者さんと本物の熊が出会ってお互いが驚く日が訪れるのもそう遠くないかもしれません。