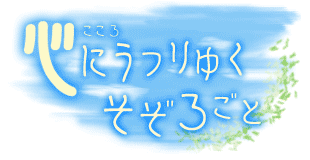 |
|
| /そぞろごとトップ /検索 /管理用 | 松本医院Home |
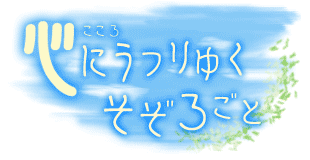 |
|
| 第246段:親からの教え再点検を |
「腹が減っては戦さはできぬ」、「しっかり食べて栄養をつけなくては」、「出された食事を残すような無作法をしないように」、「せっかくの休みだからのんびりして休養を」などと、親から教えられた年代の方々に「腹八分目で食事は残してください。
たくさん食べると病気になりますよ。
肉体労働がほとんどないので体を動かすために歩きましょう」と指導をしています。
なぜだと思われますか?
かつて「成人病」といわれた高血圧や糖尿病、ガンなどの病気の一群が生活習慣病と呼ばれるようになり、名前はすっかり定着しました。
そんな患者さんと診察室で話をしてみると多くの場合に子供の時代に親から教わった生活規範が色濃く残されています。
「もったいない」、「失礼に当たる」などという答えが返ってくるのです。
健康のために日常生活の行動様式を変えるということが極めて困難な様子が伺え、やはり「三つ子の魂百まで」ということわざを思い出さざるを得ません。
今までの生活で特に支障の起こっていない方々に「血圧が高いです」、「糖尿病です」とお話しても自分が病気とは考えられないのが普通でしょう。
生活習慣病の大半は健診などで発見された時点ではほとんど無症状ですから治療開始後に通院を中断しても全く体調が悪くなるなどということはほとんどありません。
また健康診断を受けて受診が必要といわれても1年、2年と放置していても一向に体調に変化が感じられないことが多く、あてにならない健康診断、意味のない治療というレッテルを貼られてしまいがちです。
やがて変化を感じるようになるとすでに手遅れの状態であることも少なくないのですが、無症状という力は医師や保健婦の努力を打ち負かしてしまいます。
11月初旬に禁煙の話を島根県立邑智高校で行いました。
年少者に対する禁煙指導は無症状の方への病気予防の啓もう活動の一つで、きわめて困難です。
高校生は生まれて20年に満たないわけですから、30年後あるいは40年後に起こる病気の話をしても自分が経験したことのないほどの長い年月の後の話ですから、現実感のない世界の話に終始してしまう可能性がありました。
子供の喫煙問題は看過できない健康問題ですが、極めて消極的な日本のタバコ対策に問題があります。島根県内の男子高校生の喫煙率は30%を超えています。同じく女子では10%を超えています。一度でも喫煙を経験したことのある割合はそれぞれ50%、30%を超えています。
人間は身内や友人などに異常が起こって初めて自分にも禍が襲ってくるのではないかと心配になり身を守るための努力を開始します。
生活習慣病は危機を感じてから対策をはじめても間に合わない病気と考えてもよいでしょう。
子供のときに親から教わった生活習慣が現在も通用するかどうかを再点検する必要があるのではないでしょうか?
2001年11月の山陰中央新報「いわみ談話室」から