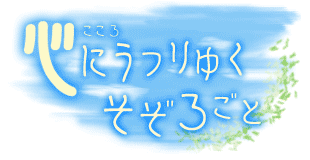 |
|
| /そぞろごとトップ /検索 /管理用 | 松本医院Home |
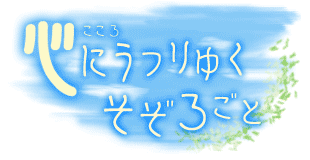 |
|
| 第248段:年をとるのはいやですか? |
子供のころには自分の年齢を若く見られると馬鹿にされていると感じていた自分が最近は年よりも若く見られると嬉しくなっていることに気づきました。
心の底に年をとることに抵抗があるようです。
患者さんにも「高齢ですから自重して・・・」とお話すると、「私を年寄り扱いしないで下さい。」と答えられる80代の方が時々おられますので、最近は「どちらかといえばお若い方ではありませんので・・・」という言い回しにしています。
老人とか老化という言葉はそんなに嫌われるものだろうかと考えてみました。
老人の老という字には年をとったという意味もありますが、経験をつんでそつがないとか、物事を良く知っている人という意味もあり、江戸時代幕府の大老とか老中などという役職に使われていた字であることを思い出せば決して嫌われる文字ではないと思うのです。
尊敬に値する人の意味もありますし、年をとったことは病気もせず生活習慣が理想的であったことの証ですのでもっと胸を張り自慢するのが当然なのではないでしょうか?
自分が70年も生きてきたのに65年程しか生きていないように若く見られるということは、経験をつんだ証が顔や体に出ていないということで恥ずかしいと考えることはできないのでしょうか?
老化すると体が動きにくくなりみんなの足手まといになったり、みんなに迷惑を掛けているからいやだと話される方が多いですね。
いつ頃からかこんな風潮が出てきたのでしょうか?
世の中に老人を敬い大切にする気持ちがなくなったことに老人が抗おうとせず自らを納得させるために自らを「老害」などという言葉で蔑んでいるのではないでしょうか?
私は益田市の中の谷、丸竹地区で10年以上前から毎年11月に、健康講話を担当しています。
地域の方々と毎年健康問題について話をしていますが高血圧や糖尿病、痴呆などの話が一通り終わり、最近は高齢者の生きがいなどということを話題に意見を交換するようになりました。
生まれたときからの年数から考えて「もう余り仕事はできませんよ」と話される方、死ぬときから逆算して「まだ10年は生きられそうだからやりたいことがある。」などと様々な答えが返ってきます。
酒瓶を見て「まだ半分も残っている」と考えるか、「もう半分しか残っていない」と考えるのと同様です。
少子高齢化社会の典型的な地区ですので高齢者自身が更に健康的な人生を送れるかどうかが地区の活性化対策そのものなのです。
年齢を考えて無理はしないで欲しいのですが、年齢を加えることに肯定的な考えがもてるようになってこそ本当の高齢者の時代になれるのではないかと考えています。
山陰中央新報「いわみ談話室」から