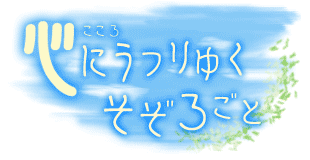 |
|
| /そぞろごとトップ /検索 /管理用 | 松本医院Home |
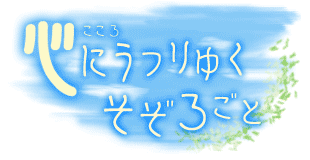 |
|
| 第249段:疲れてませんか? |
「お疲れ様でした」と声をかけながら仕事を終える風景が定着してしまいました。
いつのまにか「お先に失礼します」という言葉が用いられなくなったような気がします。
目上の人からの「ご苦労さま」というねぎらいの言葉に近い「お疲れ様でした」という言葉が部下のほうから出るようになり「アレレ?」と感じておられる方もあるのではないでしょうか?
電話の場合でも「お疲れ様です、○○です」と自分の会社に電話をしている方も増えているように感じています。
疲れをターゲットにしたリラクゼーションやマッサージなどが賑わう昨今は、日本中がお疲れモードに入っているような気がしてなりません。
先日ある高等学校で体調を調査してみましたら、一番訴えが多かったのが「疲れている、疲れが取れない」でした。
部活動や勉強に疲れているようですね。
次に「睡眠不足」、そして「目がかすむ」、ついで「立ちくらみ」、「便秘」、「下痢」、「頭痛」と続きます。
訴えの大半は休養時間が足りないことから起こっているようです。
小学校に入る前から親の不規則な生活に振り回されていた今の高校生などは疲労が蓄積された状態しか知らずに育っているのではないかと考えます。
疲れが取れているときの気持ちのよさを体感したことがないのではないかと疑ってしまいます。
今回は、ここ数年取り上げられることが多くなった「慢性疲労症候群」について説明をしてみましょう。
慢性疲労症候群は慢性の激しい疲労感が主体で、微熱、頭痛、筋肉痛などの全身症状があり、睡眠障害、抑うつ気分などの症状を伴う状態が6ヶ月以上続くか、繰り返して起こるとされています。
20歳から50歳に多く、男性よりも女性のほうが約2倍多いとされています。
原因は不明で確立した治療法もありません。一部の医師の中には本当に独立した病気かどうかまだ疑いがあるという意見もあり、すべての医師に認知されている病気だとは言えません。
疲れに加わる睡眠障害は過眠になっていることが多く、疲れているのでぐっすり眠りたい、長く眠りたいと希望して睡眠薬などを使用してかえって体調を崩している人もいるようです。
そして過眠になっている人たちの特徴は浅い眠りを長くしているために目覚めても熟睡感がないので疲れを取るためにさらに寝ようとしてしまいます。
そのため益々睡眠が浅くなり疲れがたまっているように感じてしまうのです。
人間の睡眠時間はアメリカの研究では7時間半の人がもっとも長寿という説もあり、長さよりもその質のほうが大切なようです。
睡眠の質つまり熟睡感(熟眠感)が悪い患者さんは、寝る前から「多分寝ても疲れが取れないだろうな」と考えながら布団に入っておられるケースが多いようです。
心療内科の分野では比較的多く治療に用いられる自律訓練法というリラクゼーションのトレーニングでは、寝るときに次のような言葉をイメージすると良いといわれています。
「明日の朝6時30分(自分が目覚めたい時間)になるとすっかり疲れが取れて、気持ちよく目が覚める」という文を何度も繰り返して使用します。
このイメージのときに「・・・・目が覚めるといいなあ」、とか「・・・・目が覚めて欲しいなあ」、「目が覚めてもやっぱりだめじゃないかなあ」などというような願望の気持ちや否定的なイメージを抱くと気持ちの良い目覚めになりません。
基本的には「疲れが取れて気持ちよく目覚めて、はつらつとした自分の姿をイメージする」ことが大切なようです。
しかしながら、疲れを治して欲しい患者さんのほとんどが、そんなイメージを抱くことができないほど精神的にまいっている人が多いのです。
こんな状態を「抑うつ気分」とか「抑うつ状態」と呼んでいます。
気分的に落ち込んで疲れが取れていないときにこの慢性疲労症候群のことを読むと、自分はこれだと勘違いしてしまい、原因も不明で決定的な治療法もないと知ると益々悪化させてしまうのです。
そして医師が厳密に診断基準と照らし合わせて慢性疲労症候群ではないと診断しても、短期間のうちに自分が満足するだけ改善しなければ、医師が誤診しているというような思い込みからさらに症状を悪化させている患者さんが少なくありません。
テレビやビデオでみたいプログラムが沢山ある。
インターネットや電子メールも使わざるを得ない、家族の絆も地域や社会との交流もと欲張り始めると休養の時間が最初に削られるようです。
景気の回復と同時に疲れからの回復もしていただきたいですね。
「東京ビルヂング」から