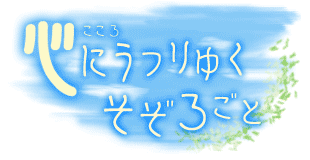 |
|
| /そぞろごとトップ /検索 /管理用 | 松本医院Home |
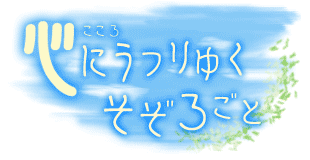 |
|
| 第252段:男と女 |
「男性を大切に、また男性には優しくしてあげてください。」
女性ばかりの集会で私が講演をしたときのお願いです。
現在の日本では男性と女性の数では女性が多く、平均余命も女性が8年近く長いようです。
80歳以上の人口比率では男性40に対して女性は100の割合です。
ある研究では精子と卵子が受精するときには男150女100の割合で受精卵ができますが、流産してしまうのはほとんどが男の子で、出生時には男105、女100の割合になるようです。
生まれてからも死亡率の高い男性がどんどん減り、40歳前後で男女が同数になり、以後は女性の割合が増え高齢者になると女性ばかりが目立ちます。
人間としての男女の成長はやはり女性が早く平均的な初潮の年齢と精通の年齢とを比べれば約1年の差があります。
生理が早く始まる女性は遅くまで生理があるように、早熟な人間は活力が良いので長寿につながります。
生理的な問題だけでなく日本国憲法での婚姻も女は16歳、男は18歳と差がついています。
何でも男女同格で同権という風潮が正しいのなら「男性の結婚年齢を下げるのが良いのか、女性の結婚年齢を上げるのが良いのか」が議論されてもよさそうなのにちっとも話題になりません。
生理学的に見れば男と女は同じではなく、それぞれの性の差があり全てを同じに扱うと返って不利益を生じることがあることは明らかです。
筋力の差や思考過程の差など決して同じとして扱ってはならないと思います。
差別ではなく区別をしてお互いの差を認め合うべきでしょう。
耐久消費財の購入などで女性の意見の通る割合が高くなっているのはご承知のことだと思いますが、それを裏付けている可能性のある統計があります。
昭和23年の統計では夫婦の年齢差は3.2歳ありましたが平成12年には1.9歳まで近づきました。
50数年前には家庭の中でも晩生の男性がリードできるほどの年齢差で家庭が成立していましたが、最近は早熟の女性に家庭を仕切られるような年齢差で結婚をしている状況がわかります。
憲法に書かれた結婚の年齢差の2歳も、家の中で全てを仕切りたいという男性の願望があるのかもしれません。
人間の活発さは男性ホルモンの中のアンドロゲンというホルモンにある程度支配されていますので、アンドロゲンが多い人は活動的であるということは良く知られた事実です。
このアンドロゲンは女性でもわずかながら作られており、やはり活動性の源にいなっているようです。
女性は50歳前後から始まる更年期の時期に一気に女性ホルモンが出なくなるために、同じペースでアンドロゲンを作っていると男性ホルモンが相対的に増えた感じになり活動的になります。
中年女性の活発さ(オバタリアンとは無関係?)はこのあたりに原因があるのかもしれません。
一方男性は30代から40代に男性ホルモンのピークを迎え徐々にその活動量が減り、劇的なホルモンバランスの変化がおきませんのでだらだらと活動力が落ち込み定年後の「濡れ落ち葉」などと蔑まされるような言葉になるのかもしれませんね。
(男は単純な一山のホルモン変化、女は複雑怪奇な現象)
生きる力の旺盛な女性は老年期も男性より長生きをしますので引きこもりがちな男性に取って代わり女性が色々な場面に活躍し始めてきます。
瞬発力には優れていても持久力などで劣る男性は女性に支えられて初めて男らしく生きて行けるのです。
オスという性とメスという性にはそれぞれの役割がありお互いが補完し合っていたはずなのです。
20世紀の単純な男女同権の意識が、動物の本来持っていたオスとメスとの役割分担にゆがみを生じさせたわけです。
21世紀の現在は、オスとメスの役割分担を踏まえた上での男女同権論を再構築しないと動物の種としての存続が難しくなるかもしれません。
男尊女卑というような言葉で一括りにして女性は抑圧されていたという考え方がありますが、実態はどうだったのでしょうか?
婿入り婚が主流だった時代や玉の輿に乗るという言葉ができた背景を考えると本音と建前の間で意外とバランスが取れていたのではないかと疑ってしまうのです。
明治時代は男性の人口と女性の人口は男性のほうが多かったのですが、最近では男性95.7に対して女性100という割合です。
今後もこの傾向が拡大して2050年には女性100に対して男性が89.6になるという研究もあるほどです。
現在のような男女同権論が猛威を振るうと男性は男性らしく生きてゆけなくなるのです。
優しく、大切に扱って欲しいと願うのは私だけでしょうか?
東京ビルヂング「カルテの落書き」から