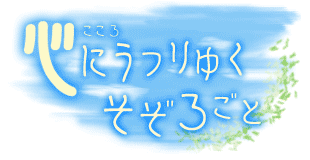 |
|
| /そぞろごとトップ /検索 /管理用 | 松本医院Home |
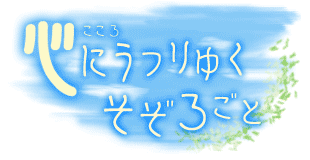 |
|
| 第253段:ドクトルの仕事 |
私が10歳のとき医業を始めて6代目の祖父が次男の私に「おまえのお父さんの跡を継いで8代目の医者になるか?」と聞かれ、訳のわからないままに「はいっ!」と答えたのが今の私の原点です。
そのやり取りのあとの雑談で「ドイツ語では医者のことをドクトルというが、それは毒をとるからドクトルというのではない。ちゃんとした意味があるから勉強しておきなさい。」といわれました。
さてそのドクトル、英語ではドクター(doctorと書きます)は歴史が古く、遠く中世の時代にイタリアのサレルノにはじめて医学校ができ1221年に大学になったようです。
神聖ローマ帝国のフリードリッヒ2世が医療を職業とする人々を認定する権限をこの学校に与え5年間学習し1年間実習を終えて試験に合格したものにdoctorと称すること許したのでした。
(日本の医学部の教育が今でも全体で6年であること、病院での実習もやはり1年ほどですし、その後国家試験があるのも同じです。)
もともとdoctorという言葉はラテン語では教えるという意味で「教える人」⇒「学者」⇒「博士」⇒「医者」と変化したものです。
ですからdoctorine(教義)、document(文書)、documentary(実録)、docent(講師)などと同じ語源になるのです。
日本ではdoctorのことは医師と名前を付けていますが、この名前は昔の中国で周の時代の「周礼(しゅうらい)」という管理制度を書いた本に始めて登場する言葉のようです。
当時の書物を見ると医官には4種類があり食医(食事療法)、疾医(内科医)、瘍医(外科医)、獣医と別れていたようです。
医の字は旧字では醫と書いていました。
この意味は「薬を与えて病気を治すこと」に加えて「その術を心得た者」だそうです。
日本では大宝律令(701年)のなかの「医疾令」で、現在の厚生労働大臣に当たる職を典薬頭(てんやくのかしら)として、その部下に助(すけ)、医博士(くすりのはかせ)、允(じょう)、咒禁博士(じゅごんはかせ)、医師(くすし)、針博士、咒禁師(じゅごんし)、針師、薬園師(やくえんし)、按摩博士(あんまはかせ)、按摩、大属(さかん)、少属(しょうのさかん)などの役職があり医術に従事し医育を担当したのは医博士と医師だったようです。
特に医博士は学術に優れた医師が任命されたらしく、明治21年(1888年)学位令ができたときに優れた医師としての称号となった医学博士は1200年近く前に書かれた大宝律令の文言から出ているのです。
(私も恥ずかしながら医学博士の端くれですが、これを調べてみて大変な歴史をもった言葉だと知りました。)
ところが立派な意味と伝統のある「医師」ですが仲間の間では色々と謙遜や中傷の言葉があり、藪(やぶ)医者にもなれないほどの医者を筍(たけのこ)医者(小泉内閣メールマガジン第2号で一躍有名な言葉になりました。)とか、藪は向こうが透けて見えるからまだましで、向こうが見えないのは土手医者とか、研究室で犬を使った実験を繰り返しているとdoctorならぬdogtorと称したり、どんな病気で受診しても漢方薬の葛根湯を処方するので馬鹿にして葛根湯医者と言ったり(ところがこれで結構治るので重宝)、耳の穴や鼻の穴を診ることが多い耳鼻咽喉科の医師を「穴掃除」と呼んだり眼科の医師を「目洗い」、手術ができないので「何にもでき内科」などという場合もあるようです。
(多数割愛あり)
ドクトルや医師という言葉にはさまざまな歴史や意味があり、それを知ることが医師の第一歩と祖父は言いたかったのかもしれません。
祖父が他界してすでに30数年、父も20年程前に帰らぬ人となりました。
英語の得意だった父は「内科医のことを英語ではphysicianというが、この言葉は『人を自然の健康状態にする者』という意味だから、健康状態を取り戻すことができなくなり、死の直前の患者さんにあれもこれもと治療を続けるのは本来の姿ではない。もちろん内科医だけでなくその考えは外科やその他の考えにも通じる。」と話してくれたことがあります。
医師としてどのような倫理観を社会が求められているかと考えてみるよりも、医師やdoctorという言葉の由来を学んでみるとあるべき姿が見えてくるような気がします。
医療費や医療保険制度の改革の論議が盛んになっていて、しきりに医療費の抑制が叫ばれています。
命はお金には代えられないという気持ちを持つ人たちが、なぜ安い医療を求めるのでしょうか?
自分たちがどのような医療を受けたいのか、医師はどのような医療をすべきかという観点からの論議が必要なのではないでしょうか?
価格破壊の時代ですが質の高いものを提供する業種での価格は上昇しつづけています。マニュアルブック通りの均質で低レベルの医療に体をゆだねたいですか?
ドクトルや医師の言葉の原点から湧き出る医療は質が高くお値段もそれに見合ったものになるはずですが・・・・
参考文献:楽しい医学用語ものがたり、医歯薬出版(株)著者:星和夫
東京ビルヂング「カルテの落書き」から